価値と価格はしばしば同義のように用いられるが、現実にはまったく異なるものだ。
たとえば、思い出プライスレスという表現は端的にそれを表している。思い出は本質的に価格がつかない。思い出の場所の入場料を払ったとしても、その価格が思い出の価格だ、とはならない。価値はその人の感性から生じる主観である。
一方、価格は観測可能な客観で、思い出の場所の入場料は、価値ではなくても価格には違いない。この価格の決定は需要と供給の均衡と学校で習う。しかしそれは完全競争市場なる前提があるが、現実にそんなことはありえない。値札はハッキリ見えるが、その内訳は見えない。
実際、価格の内訳にどれほど価値と言うべきものがあるかはわからない。価値がそのまま価格になるわけではない。価値はしばしば価格以外のものを求める。それは苦労であったり、汗であったり、時間であったりする。バンドTはライブハウスで買うから意味があるのだし、山頂の景観は自分の足で登って見るから意味がある。
そういうことをまるっと無視したのが転売ヤーという連中なのだが、彼らは実際蛇蝎のごとく嫌われている。金銭にかえるべきではないものをかえることを、人は無粋と呼ぶ。
一方で、この逆のパターンもある。当然価格がつくべき価値に、価格がつかない、というパターンだ。そんなバカな、と思うかもしれないが、実際よくある。実際、大企業が力関係を利用して中小企業の製品を買い叩くのは世間的にも非常に叩かれるが、それは支払うべき対価を力関係で潰していることが明らかだからだ。
しかし、別に力の悪用などせずとも、価格を極限まで下げられるものがある。ソフトウェアだ。ソフトウェアは原理的に誰でもコピーができる。それも無限に。そのコストは0に近い。したがって、ソフトウェアの価格はそのままだと0になる。
これではソフトウェアは商売にならない。なので、ソフトウェアというより別のところで料金が取られる。おもだったところで、サポート、ライセンス(所有権)、サブスク(利用権)。
それぞれ成功モデルがあるのだが、もっとも成功しているのがサブスク、なのはそうだろう。サブスクは、ソフトウェアの複製コストが0であることを逆手に取り、複製の権利をプラットフォームが独占し、配信してアクセス権を売ることで収益を得るモデル、と言って良い。Windowsなどはサポートの打ち切りとアップデートの強制で、サブスクモデルを擬似的に達成しているとも言えるが、ユーザはアップデートしない選択も可能だ。しかし、サブスクにその選択肢はない。
この独占を実現するのは端的に力関係である。そう、大企業が中小企業を買い叩くのと同じ、力関係だ。転売ヤーが市場在庫を枯渇させて流通を抑えることによって得られる、力関係だ。力関係が、価格を作る。そしてプラットフォームが十分な力を得て、あらゆる人が使わざるを得なくなった時、あらゆる人との間に力関係による価格が生まれる。結果、価値と価格が乖離する。
そして、価格と乖離するのは価値だけではない。価値を形作っていた、人間そのものが、価格から乖離していく。物流、介護、食料の生産、インフラの維持、人間の価値ある仕事に価格がつかず、広告、PR、無意味なアップデートに価格がつく。
今、その最終局面にあるんじゃないかね。
<関連記事>



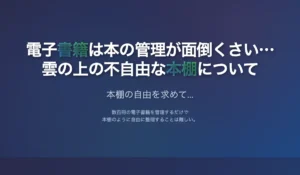



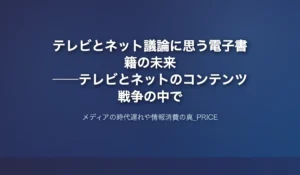
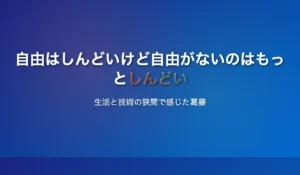
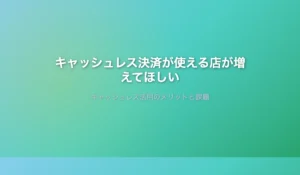
コメント