以前、「転売ヤーはなぜ嫌われるのか」という記事を書きました。このテーマは関心ある人も多いと思うんですが、カジュアルなタイトルとは裏腹に、15年以上個人的に考えてきたことでもあったため、僕が書いてきた記事の中でも長大かつ異様に複雑な構成の記事になってしまいました。さすがにちょっとなぁと思われたので、本質を抽出したいていの人が読みやすい形になおしてみました。
これはまぁ、「転売ヤーむかつくけど、資本主義では当たり前!って言われたらぐぬぬ……」ってなってしまう人向けの言語化の一種だと思っていただければ。
制度的には否定できない、けど……
まず制度面から見た話なんですけれど、転売は資本主義的に否定できない、ただし問題がないとも言い切れない、くらいかと思います。やっていることは値札の貼り替えでしかないので、それ自体は基本的に規制できないしすべきでもありません。
一方で、勝手な値上げが認められるなら小売店がそれをやるはずなんですが、実際には彼らはそれをやりません。なんならお前は転売ヤーじゃないのかと疑い、ゲームであれば「このゲームのキャラを言ってみろ」と踏み絵を踏ませたりすることもあるわけです。
つまり、法的には問題がなくとも、そこには商売人としての倫理的・道義的な責任が存在します。金さえ出せばなんでも売るよ、なんていう麻薬の密売人みたいなやつは信用されないわけです。長期的な信用にも繋がることなので、売る相手を選び、市場全体を見て本当に必要な人にあるべき価格で届けるようとする姿勢は、経済合理性の観点からみても決しておかしなことではありません。
不粋なんです
これで話を終えてもいいんですが、個人的にはもう一歩踏み込んで、長期的な信用のためというが、その信用の源泉はなんなのだろうか、というところまで考えてみたいと思います。結論があるような話ではなくて、あくまで自分はこう思う、という与太話ですが。
これは文化の担い手としての矜持、と言えるものだと思います。
僕らは物を売ったり買ったり日常でするわけですが、それは単に金銭とモノを交換しているだけではありません。欲しかったゲームを買った時、スーパーでキャベツを買った時には絶対に得られない興奮や歓びがあります。これは金銭で換えられるものではありません。
その金に換えられないはずの歓びを金に換えるのが転売ヤーという連中です。本来は金に換えられないものなので、場合によっては青天井に上がります。それは決して需要と供給などという言葉で表されるものではなく、文化に対する挑戦であり冒涜とすら言えるモノです。こういう行為を、我々は古来より野暮とか不粋と言って嫌います。
これは文化を愛する人なら多くの人が共有する感覚です。それがわかるからこそ、その文化の中で商売をする小売店はやらないのだし、またそれをやってしまう転売ヤーに対しては、大きな嫌悪感が生まれます。
金にしてはいけないものがこの世にはあります。お前それ、金にするんか、っていう。そういうものはあるんです。母の形見を秒でメルカリに出す奴いたら引くでしょ。それは法律で規制することじゃないけれど、だからといってやるんかお前っていう。本質的にはそういうことです。
詳細版
この記事は色々な問題を省略した簡易版なんですけれど、本質的なところはこんなもんかと思われます。もし詳細版に関心ある方は是非下記にお越しください。色んな意味で僕っぽい記事だなと思います。色んな意味で……。


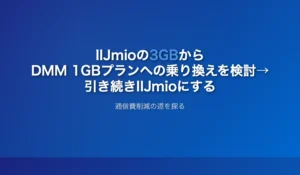
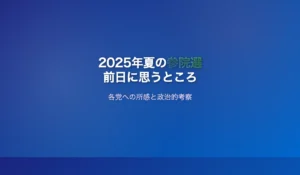





コメント