トランプ大統領が例によって例の感じで、MSの幹部であるリサ・モナコの解雇を要求しているらしい。この非常に露骨な民間への政治介入は、今が転換点であることの象徴的事例なのではないかと思えて、注目している。
リサ・モナコについて
まずリサ・モナコについてだが、バイデン政権で司法副長官、オバマ政権で国土安全保障担当大統領補佐官を歴任した元政府高官であるらしい。で、2025年7月にマイクロソフトのグローバルアフェアーズ部門責任者に就任した。
これは日本だとどう見ても天下りです本当にありがとうございました、という感じなのだが、アメリカだと普通らしい。というのも、アメリカは政権交代の度に数千人規模で政治任用者が交代するので、交代させられた彼らが民間にいくのは当然、ということだ。つまり大企業と政治が滅茶苦茶近いってことだよねと思いつつ、アメリカはそうらしい。
いずれにせよ、こういう経歴だから、リサ・モナコは確かに完全に民間人とは言い難いことは事実ではある。
ヘイヘイMSビビってる
しかしそれにしたって、一応今は民間人なのだから、クビにしろおらぁ、とはあまりにも露骨である。で、これに対して今のところMSはダンマリであるらしい。ここまで舐められたら、反論してもおかしくないと思うんだけど。5年前なら、即座に反論してたんじゃないかな。まぁ今も準備中かもしれんのだが。そもそもトランプとて5年前ではここまで露骨になれんかっただろう。
見ていて思うのは、やはり企業と国家の関係が、再び変わろうとしているのだろうか、ということだ。
やはり先ず影響として考えられるのは、ウクライナ戦争だろう。グローバル企業といえども、結局は本国政府の方針には従わざるを得ない。ロシア制裁で一夜にして市場から撤退せざるを得なかった各社の姿は、「企業に国境なし」という幻想を打ち砕いた。
世界も全体的に荒れていて、EUでさえもGAFAMに対する態度はけっこう強硬になっている。実際、EUはGoogleに多額の制裁金を課しているし(「トランプが「関税で報復」か? Google日本元社長が憂慮、独禁法違反でグーグルに5千億円の制裁金を課したEUが自ら締めた首 - まぐまぐニュース!」)、Appleはストア外のインストールを認めざるを得なくなった。
こういう中で、EUに毅然と反発しているのが他ならぬトランプだったりするわけだ。さぞ頼もしいことだろう。つまり、GAFAMは明確に「アメリカ企業の保護」を必要としている。中国との技術覇権争いも激化しているし、これからグローバル企業は他国の国家とぶつかることも多かろうね。
政府とMSどっちが好き?
しかしまぁここまで露骨だと、市民からの反発もありそうではあるんだが、どうだろうな。というのも、アメリカ人が政府を好きとは思わないが、かといってMSを好きかと言うとねぇ。
Windows 10のサポート打ち切りもそうだけど、とにかくビッグテックの強権ぶりは目に余る。市場を独占してやりたい放題して、サブスクとか実質徴税みたいなもんだから、EUもブチ切れている。
それは自由競争の結果だというかもしれんのだが、しかし情報技術はネットワーク効果の大きさと標準化という特殊な事情があるので、確かに地位の確立までは競争していただろうが、その後は果たして競争しているか?というと疑義がある。今からiPhoneに勝てそうもないのは、技術の問題ではなく市場の問題のほうが大きいだろう。
そんなわけで、彼らは気兼ねなく思想信条に基づいて垢BANしたり、誰も求めてないアップデートしたりするだけでよく、実際特にここ15年くらい、ソフトウェアやサービスが本当の意味でよくなかったのか、というと個人的には疑問である。
ハッキリ言えば彼らの振るまいはもはや政府のようなもので、今読んでいる本ではソ連 2.0などと呼ばれていた。
しかし、選挙で選ばれた政府と違い、企業には民主的な正統性がない。市民は政府に対しては選挙や抗議で意思表示できるけれど、企業に対しては「嫌なら使うな」と言われるわけだ。うるせぇWindows 10使わせろ。
ということで、MSはもちろんGAFAも別に好かれてはいない半政府扱いだろうから、トランプにああだこうだ言われても別段同情されんのではないか。
歴史的転換点としての意味
そういう社会的背景もあって、トランプ節炸裂してんのかなぁ、と思う。確かに露骨なんだけれど、それが許される感じになっているというか。企業は企業でやり過ぎてきたのはそうだろうな。
なので、この揺り戻しはこれからさらに続くと思われる。この一件は確かに露骨なんだけれど、その露骨さはトランプだからというより、時代が変わっているからではないか。まぁトランプ自体が時代の要請で生まれたような気もするし。
ということで、これは企業が国家を超えるとまで言われていた時代が終焉したことを、明確に示す象徴的な出来事かなぁと思って、注視している。

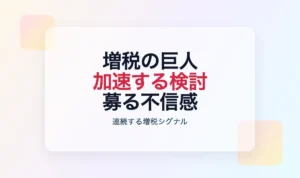

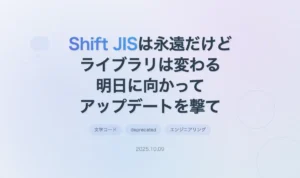





コメント