AWSの責任共有モデルはクラウドに関わるものなら誰でも知っていることで、今さら僕が言うことはなにもない。しかし、彼らが共有したという責任について実際に何かしたのを見た人はほとんどいない。まぁ探し出せばクレジットの払い戻しくらいは事例が見つかるだろうが、果たしてそれがサービスの根幹としての責任と言えるのかどうかは疑問である。
しかしそれにも関わらず、AWSは売れまくっている。この事から、責任共有モデルについて、一定程度評価されている、と見るのが妥当であろう。だが先のとおり、定期的なイベントとなっているAWSの障害によりサービスが停止しても、別にAWSがユーザに代わって顧客に謝罪しに行くわけではない。
何も変わっていない。AWSは決して障害を起こさないわけではないし、障害が起きればサービスは停止する。ただ、オンプレの障害の場合、エンジニアは針のむしろになるかもしれないが、あの業界最大手巨大企業Amazon率いるAWSの障害であれば、仕方ない、ということになるかもしれない。少なくとも、自社のエンジニアが受けたかもしれない責めが、そのままAWSに向かう、というわけではなさそうだ。
こうなると、そもそも大した責任があったわけではないのではないか、という疑問が生じる。実際、サービスが停止したからといって、別に誰か死ぬわけでも会社が破綻するわけでもない(というよりそういうサービスでクラウドの利用は慎重になる)。エンドユーザから訴訟を起こされるわけでもない。まぁクレームはくるかもしれない。だがそのクレーム処理は結局自社でやるのだし、エンドユーザからすればインフラがAWSなのかオンプレなのかは知ったことではないし、クレーム処理班もそれは同様である。
つまり、元々大してあるわけではなかった幻の責任を膨らませ、現場のエンジニアに不当に押し付けていたのではないか。だからエンジニアがその責任をAWSに投げた時、AWSは障害を起こさないわけでもなければ、会社に代わってエンドユーザに詫びるわけでもないにも関わらず、その責任は幻であったので、大した問題にならない。AWSが本当に見抜いたのは、インフラの責任ではなく、組織の不条理だったのではないか。
これは責任共有モデルというより、責任幻想モデルというほうが相応しいかもしれない。

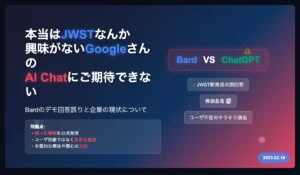

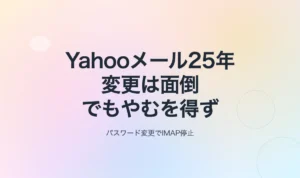
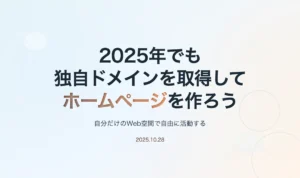


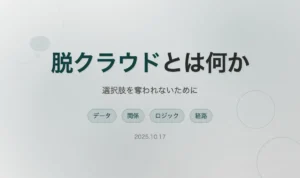
コメント