AWSでもGCPでもAzureでもなんでもいいが、多くのクラウドサービスは本質的に何も提供していない。彼らの言う機能も非機能も虚飾に過ぎない。では何故彼らの商品を世界中の人が買いまくるのだろうか。エンジニアに至っては信仰に近いものすら抱いている。
それはもちろん、エンジニアにとって神の代理人に等しい存在だからである。なぜそんなにも尊いのか。彼らのサービスが素晴らしいから?そうではない。
エンジニアにはPC一つ買うのも渋る会社が、AWSの発行する請求書については文句を言わずに払うからである。エンジニアは自社の資産となるサーバーは買えないが、AWSのEC2インスタンスは自由に借りることができるのだ。
つまりクラウドとは、決裁権である。
それだけではない。自社サーバが落ちればエンジニアは責められ針のむしろになる。一方EC2インスタンスであれば、自分でやるより多くの場合で可用性が高く、しかもたとえ落ちたとしても、針のむしろとまではいかないかもしれない。だってどうしようもないのだから。これは、個人が交通事故に遭うと、なにか不注意があったのではないかと個人の責を疑われることがある一方、災害に巻き込まれれば、ただ同情されることと似ている。
つまりクラウドとは、免罪符である。
決裁権と免罪符をくれるのだから、そりゃ信心も深まるというものだ。
しかし決裁権も免罪符も、現場に仮初めの安らぎをもたらすだけで、社会全体を見れば別になにかよくなるわけではない。請求書の発行元も、障害の原因も、社会には関係が無い。社会全体でクラウドというものを見た時、何かよくなったのか、正直よくわからないと思う。
そもそも現場の決裁権のなさが不適当だったのではないか。また、実態と見合わない過度な責任を負わされていたのではないか。いずれも組織の問題だ。それをAWSが一部引き受けた——あるいはそのように錯覚させたとして、問題の根本は変わらない。
つまりクラウドとは、技術革新ではなく、組織的抑圧の代替装置である。
今日もどこかで、利用者のいない可用性99.9%のプロダクトがローンチされたことだろう。
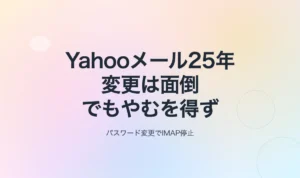



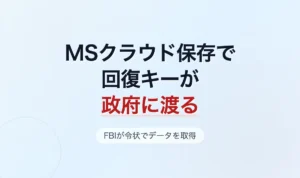


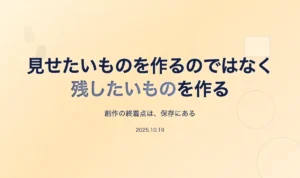
コメント