エンジニアと仕事をしていれば、「技術的には可能です」という言葉を一度は聞いたことがあるだろう。エンジニアなら言ったことがあるかもしれない。この言葉は字面とは裏腹に政治的なニュアンスを伴うため、使い方には注意が必要だ。もっとも、若手の間はそもそも政治性に中々気づけなかったりする。気づけなかった。
似たような政治的な言葉として「決めの問題」、「できるできないではなく、やるやらないの話」、直截な言葉としては「それは政治ですね」なんて言ったり言われたりなんだり。
こういうやりとりはしんどくて、言う度に、なんだか魂がすり減るというか、澱むような感覚がある。それは或る意味当然だ。技術的な純粋性とは別の話だから。それで、僕のような出来損ないプログラマにも欠片くらいはある職業的威信が、お前は技術の道を選んだ職業人として不誠実なんじゃないか、と僕を苦しめるんだな。
責任回避としての技術的な正しさ
なんだかんだで、僕なりに組織人やっていたんだなぁと思う。今も一応そうなんだろうか。形式的には組織はあるが。まぁちょっと離れたから、今まで自分やってきたことや、世間で起きていたことについて、ここ一年以上、ずっと考え混んでいたような感じだ。
それで振り返って思ったのは、なんというか、正しさが尊ばれる世界になっているな、ということだった。「技術的には可能です」というより、「これが技術的に正しいです」って感じ。「これがベストプラクティスです」ベストプラクティスなら仕方ない!
これは相手と向き合うというより、突き放すような感じがある。相手との関係よりも、正しさなるものを優先しているような。
ここにきて、これはなんだか、今流行の(ちょっと遅れている?)「政治的な正しさ」のようだなぁ、と思った。正しさなるものがどこかで決まり、それに乗っかっていればとりあえず安全で、逆らうとつるし上げ。勉強不足、理解不足。時代についていけないロートル。
自分が良いと思うものではなく、良いということになっているものを追い続ける虚しさよ。だがそれでもやるのは、正しさに乗っかるのが組織人としてけっこう合理的だからだ。なにしろそうしておけば、何かあっても言い訳できる。やるべきことをやっていたと言える。そういうことなら、仕方がない!……本当に?
職業的威信としての技術的な正しさ
しかし考えてみると、「技術的な正しさ」は本来的には純粋なもののはずだ。実際、技術的に正確であることや、また筋が良いことは、技術者なら尊ぶのが当然だ。たとえそれを主張することによって、不利になったとしても、言えなければならないものだ。ただの一介の人間が、その正しさのために強くなれるはずのものだ。それは責任回避とはまったく逆のことだ。
そもそも絶対的に正しいものなど存在しないことは自明であるとわかっている中で、不合理にも正しさを主張するとすれば、いったいそれは何故なんだろうか。
それはもはや当人にもわからない。ただ、言わなくてはならないのだろう。そこに何かがあるとすれば、職業的威信、プライド、魂、人生、そういった言葉表現されるようなものではなかろうか。
わからないが、まぁ少なくとも、ベストプラクティスのため、ではなさそうだ。
技術は嘘をつかない
職業エンジニアには二面性がある。
職業エンジニアとは、結局のところ組織人であり、社会人である。技術が世界を変えるのではなく、世界の要請で技術が変わる。ジェームズ・ワットは趣味で蒸気機関を改良したのではないし、インターネットは軍事の世界で産声をあげた。求められるものが形になる。
政治的な正しさが流行る世情においては、技術的な正しさも求められよう。これは同根だ。エンジニアが正しくあろうとしているのではない。世界が正しくあろうとしているのだ。正しい手続き、正しいプロトコル、正しいシステム、正しい価値観。職業エンジニアは今、正しさを生んでいる。それは責任を引き受ける強さではなく、逃れられる道筋を与えてくれる。
一方で、アマチュアリズムというべき精神を、誰しも抱き続けていることもまた事実である。
大昔、現場で電気の人が好んで使っていた言葉に、「電気は嘘をつかない。嘘をつくのは人間や」というものがあった。これは全然違う会社の、全然違う地域、さらに強電とエレクトロニクスのおっちゃんがそれぞれ言っていたので、あちこちで言われていたのではなかろうか。後年、「データは嘘をつかない。嘘をつくのは(略)」と言うモダンなソフト屋をネットで見たので、コピペのごとく古来より言い伝えられし決め台詞なんだろう。
業界も年齢も違う人たちが、同じようなことを言っているのは面白い。この言葉から、その職業において、その人が大事にしているものが何かわかる。電気にせよデータにせよ、その人はそこに真実を見出している、ということだ。普通の人は電気に真実を見ない。電気に電子以外の何かがあるように見えるのは、その人が電気屋だからだ。
しかしいずれにせよ、世の中に絶対的に正しいものはない。技術的な正しさは、それが純粋なものであれ商業的なものであれ、幻想には違いない。幻想は自分にしか見えないし、共有できたところで共同幻想に過ぎない。追い求めても詮無いもの、という意味では結局同じなのかもしれない。恐らくはどちらもそれなりに必要なものだから、適当な塩梅で付き合うのがいいだろう。
このように言うと虚無的に思われるかもしれないし、実際そうかもしれない。ただそれでも一つ思うことがあるとすれば、技術は嘘をつかない。これは多分、そうだと思う。
関連するようなしないような記事

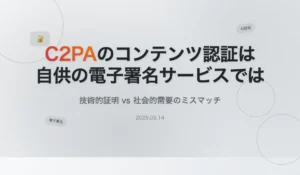
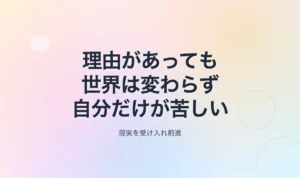
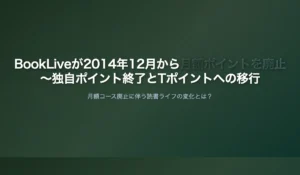
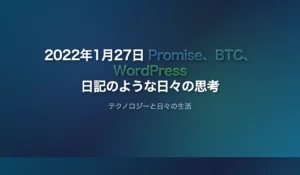

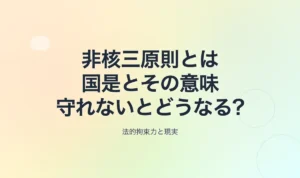
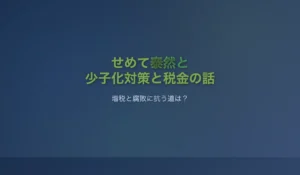

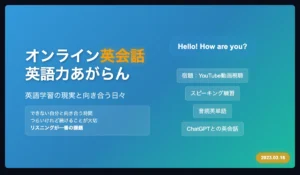
コメント