「世界の猫を喜ばす」
こんなキャッチコピーを掲げていた会社で、最近一般職の新卒社員の9割近い人数(16/19)が就職を辞退するというニュースが報道された。それは同社のキャッチコピーに共鳴していた多くの愛猫家を深く失望させたようで、「人に優しくできない会社が、猫に優しくできるわけがない」というようなコメントを数多く見た。もっともな話だ。しかし、人間に対してやたら厳しい動物愛護者というのは、見たことある人が多いのではないか。
が、本記事のテーマは、理念と矛盾した企業の態度でも、動物愛護者にいる一部の歪な価値観の人たちでもない。社会における「助ける」とは何かであり、その実践についてである。
「助ける」にある3つの視点
「助ける」は美しい行為とされることが多いが、その実践は案外難しい。「助けたほうがよいに決まっているじゃないか」と思う人は、たとえば「電車でお年寄りに席を譲るべきか」について考えれば、人によって意見が異なることも、また状況によって行動がしばしば変わることも理解できるだろう。少なくとも、すべての人が「必ず席を譲るべき」とは思わないことは想像に易い。何故か?
まず、助けるを視点に応じた3つの要素に分解したい。
一人称の「助けたい」
「助ける」について考えた時、まず思い浮かぶのは一人称の「助けたい」である。これは人を助けるうえで根幹であり、実際に「助ける」をしたとき、「助けたい」と思っているかどうかはモチベーションに大きく影響する。
「助けたい」は助けるうえで重要な想いだし、また多くのことについて「助けたい」と思えることは、その人の仁徳として尊ぶべきことだろう。しかし、助けるとはそれだけのことではない。
二人称の「助けられたい」
「助ける」は「助けたい」だけではない。次に考えるべきことは、「相手は助けてもらいたいのだろうか?」つまり二人称の「助けられたい」であろう。これについて深く考えられるようになることは、子供から大人への成長の過程で必要なことの一つだ。
先の「電車でお年寄りに席を譲るべきか」について考えれば、相手が「自分はまだまだ若い!席を譲られるなんて年寄り扱いされたくない!」と思っている可能性は常に否定できない。「席を譲られ、歳を感じてしまいちょっとショックだった」という人の声は実際にある。
つまり「私は席を譲りたい」と考えているにも関わらず、「席を譲られたくない」と相手が考えているかもしれないわけだ。また、その逆パターンもある。たとえば非常に疲れているとか体調不良であるとかで、「私は席を譲りたくない」のだが、相手は「席を譲ってほしい」と思っているかもしれない。場合によっては「席を譲りたくない」し相手も「譲られたくない」こともあるだろう。
このようなことを考え始めると、少なくとも「お年寄りがいたら席を譲るべきだ」は常に成り立つわけではなさそうに思える。助けるのは「余計なお世話」かもしれないのだ。
三人称の助けるべき、助けられるべき
さらに混乱させられることに、もう一つの視点がある。それは「助けるべきか」あるいは「助けられるべきか」という三人称の視点である。社会的な視点と言っても良いだろう。
この視点においては、「電車でお年寄りに席を譲るべきか」については基本的に「譲ることが望ましい」。ただ「譲らなければいけないわけではない」し、また「体調不良の人や、妊婦や身体に障害がある人などが無理して譲ることはない」だろう。
難しいのは、社会というのは流動的かつ時と場所による抽象的なものなので、決まった正解があるわけではないことである。電車の例では、比較的社会的な見解が統一されていると思われるため、さほど迷うことはないかもしれない。しかし世の中では立場によってまったく逆の見解になるような複雑な事象が多い。
視点によって見え方が異なる
たとえば非常に政治的なイシューになるが、「北朝鮮の拉致被害者はどんな手段を講じても助けられるべきか」について考えてみよう。
これはほとんどの日本人はまず「助けたい」と思うだろう。だがもしかすると、他人のことなので「どうでもよい」と感じる人はいるかもしれない。家族についてネガティブな思いがある人ならば、「助けたくない」とすら感じている人はいるかもしれない。問題がなければもちろん助けてあげたいけど、問題があるならちょっと考えるかなぁ、という人もいるだろう。人によるし、状況にもよる。
相手について考えた時、日本に帰りたい気持ちも、家族に会いたい気持ちも当然あると思われるが、もしも洗脳めいたことをされていた場合や、自分が奪還されることによって大切な人(現地で作った家族など)が危ない立場に置かれるリスクがあった場合、必ずしも「助けられたい」だけではないかもしれない。その心中は不明確かつ複雑であることが予想される。
社会的には当然「拉致被害者は奪還すべき」だ。しかし、もしそのために「殉死覚悟で自衛隊を投入する」「場合によっては戦争になる」リスクがあるとすればどうだろうか?それでもやるべきだという考えもあれば、もっと慎重に手段を考えるべきだという考えもあるだろう。いや、それどころか「そもそも拉致などない」と主張していた政治的集団すらあったことも事実である。つまり、統一された社会的な見解はない。
各視点の「助ける」に影響する現実の課題
なぜ各視点で見解が異なるのだろうか。そこには感情的なものだけはなく、客観的な課題もありそうだ。それぞれの視点に影響を与える諸要素について考える。
コストがかかる
「助ける」にはコストがかかることが多い。それが電車の例のように、自分のその瞬間の労力だけであれば大した問題にならないが、それが他者を巻き込んだり、まして国家そのものが動くような事態になると、あらゆる視点で「助けたい」し「助けられたい」し「助けるべき」だとしても、「コストの問題で非常に厳しい」ということはありえる。
このコストの問題は、一人称、二人称、三人称の観点にそれぞれ大きな影響を与える。
複数の方法がある
いざ「助ける」ことになったとしても、その方法には様々なものが考えられる。電車の例一つとっても、単純に「席を譲る」だけではなく、「(相手の気持ちがわからないため)次の駅で降りる振りをする」とか「何も言わず無言で席を立つ」「どうぞと言う」など細々とした違いは出てくるものだ。
これくらいならば大した違いではないが、拉致被害者の例であれば、「あくまでも外交的な手段でやるべきだ」という人もいれば「たとえ物理的な攻撃を伴うことになったとしてもやるべきだ」などその方向性は大きく異なる。つまり、「助けたい」者同士でも、その助ける手段で対立しうる。
必ず成功するわけではない
助けようとして失敗することはよくある。場合によっては、事態をより悪化させることもしばしばだ。かけたコストはかえってこないどころか、より大きなコストが必要になる。さらに、前述したように助ける手段は複数あるため、その手段の選択で対立していた時、ある手段が失敗した場合、その手段を選んだ人たちは別の手段を支持していた人たちから大いに非難されることも考えられる。
しかし世の中に絶対成功するものはない。失敗のリスクは常にある。失敗のリスクを恐れて、「助けたくない」「助けるべきではない」と感じたとしても、それは自然な感情であろう。
また、ものによってはそもそも成功の定義が難しいことも多い。たとえば動物愛護のような抽象的かつ大きな課題では、何をもって成功したと言えるのか、極めて難しい。
「助ける」のはなぜ難しいか
以上の3つの視点と、を見ていくと、「助ける」が何故難しいかも見えてくる。
わかるのは一人称の「助けたい」だけ
助けることが難しい理由の一つは、一人称の「助けたい」しかわからないことである。人の気持ちは見えないので、二人称の「助けられたい」については常に不確かだ。三人称の「助けるべきか」についても、複数の見解があり、統一された見解は多くの場合ない。
ゼロイチではない
「助けたい」「助けられたい」は完全なゼロイチではない。「もちろん助けたい、でもそのための犠牲が大きいと言われると尻込みしてしまう」は自然な感情だろう。電車の例でも「お年寄りに席を譲りたい気持ちはあるけれど、否定されたら嫌だし、そもそも自分も今日はとても疲れているんだよなぁ……」という時には、「譲りたい」気持ちと「譲りたくない」気持ちの両方がある。
さらに、より深く見ていくと、「三人称的な視点が一人称の気持ちに影響を与えている」こともわかる。これはたいていゼロでもイチでもない、複雑な心境に繋がる。こうなると、明確と思われた自分の気持ちすら実は曖昧でわからなくなっていく。
一人称、二人称、三人称の視点で矛盾した結果になる
ここまでの例を見ていけば、一人称、二人称、三人称の結果は必ずしも一致しないことがわかるだろう。これらがすべて一致すれば基本的に問題ない。問題は矛盾した時だ。そして、しばしば矛盾する。いったい、どの視点を優先すべきなのだろうか?それはケースバイケースである。
場合によっては、「自分は助けたくない」し「相手も助けられたくない」と思っているにもかかわらず、それが社会的に必要であれば、「助けなければいけない」し「助けられなければいけない」こともあるのだ(仕事と呼ばれるものにはそういうものが多いかもしれない)。
失敗のリスクがある
「助ける」は失敗することもよくある。先に各視点に影響する現実上の要素として、「コスト」「手段の選択」「成功の定義と成功率」をあげた。
失敗すると、コストが無駄になるばかりかより大きなコストが求められるリスクがあり、別の手段を支持する人たちから非難される。しかし100%成功することなどなく、そもそも成功の定義が曖昧なこともよくある。このコストとリスクの問題は非常に大きい。
「助けたい」しかない人
社会において苦労したり、また怒りを買ったりすることがある人というのは、たいてい「コストやリスクを顧みずに」「助けたい」だけが突出した人である。そういう人たちは、「弱者保護」系に行き着くこともあるようだ。そういった社会活動は、二人称、三人称の複雑で厄介な問題が省かれる(ように見える)ため、一人称の「助けたい」だけで済む(ように見える)ことは大いに関係しているように思える。
たとえば動物愛護について考えよう。
- 一人称: 動物を助けたい
- 二人称: 動物が助けられたいかを判断するのは難しい
- 三人称: 基本的に動物愛護は良いこととされる
二人称と三人称の厄介な視点について、ほとんど考えずにいられることがわかるだろう。
もちろん、現実的には問題は複雑である。人それぞれの立場・信条があり、コストがあり、手段があり、リスクがある。したがって、本当を言えば、二人称の問題も三人称の問題も存在する。だから、一般的に良いとされる社会活動でも、現実の複雑性を無視していると見做されれば、Twitterなどで人々の本音を見ていくと、必ずしも良く思われていないことがわかる。たとえば、「世界の猫を喜ばす」はずの会社が、実は社内の人間を虐げているのではないかという疑惑が生じると、「相手や社会のことを考えずに、ただ自分がやりたいことをやっているだけ」に見えてしまうわけだ。
我々が本当に尊ぶ存在は、あらゆる視点について熟慮し、リスクを承知してなお「助ける」人たちであって、自分の感情の思うがままにやりたい放題している偽善者ではない。たとえその感情の一つに「助けたい」であったとしても、「助ける」にはコストとリスクがあり、また立場によって見え方も変わる。そういったことを考慮せずにただ「助けたい」では、助けられないのである。
バランスを欠いた人たち
ここでは一人称の視点である「助けたい」だけの人について例をあげたが、世の中には二人称の「助けられたい」、三人称の「助けるべき」「助けられるべき」だけが突出した人たちもおり、いずれもバランスを欠いている。色々、思い当たるんじゃなかろうか。
ここまで見てきたように、「助ける」には一人称、二人称、三人称の視点があり、それぞれの結果はゼロイチではないうえに不明瞭で、しかも相互に作用しあう。そして「助け方」には複数の方法があり、それぞれで異なるコストが発生する。そして常に失敗のリスクがある。
このように見ていくと、「助ける」とは複雑な社会的な行為であることがわかる。それを我々は子供から大人に至る成長の過程で少しずつ学んでいく。その難しさから、正直真面目に考えれば考えるほど、何もしたくなくなってくる。実際、もう何もしたくねぇ、という大人は多い。考えるのをやめて、ただ「助けたい」という「欲望」にだけ突き動かされてしまう人もいる。「なんで助けてくれないんだ」と駄々をこねるだけの人もいる。いずれも良いことではない。
「助ける」とは「助け合う」こと
確かに、自分の気持ちだけに正直でいるのは、良い結果にはならないだろう。相手のことを考えて、社会を見て、そこにかかるコスト、リスク、そして失敗した時に何が起きるかについて一通り思いを馳せて、そのうえでなお「やるべきだ」と感じられるのであれば、多分それはやるべきなのだし、それをやって結果に責任を持つのが、大人と呼ばれる存在なのだと思う。
なんだかとんでもなく難しいことを言っているように見えるかもしれない。が、実はそんなにたいしたことではない。自分は「助ける」だけではなく「助けられる」存在でもあることを認めればよいのである。二人称とは相手から見れば自分のことであるし、三人称の視点には当然自分も含まれる。
つまり、我々はただ「助ける」のではなく、時に「助けられる」、そんな「助け合う」存在なのだ。
結局我々は不完全だし、またそんな我々が作る社会も不完全だ。不完全だからこそ助けがいるし、不完全だからその助けもしばしば間違える。間違えれば、助けてもらう。重要なことは、不完全でも、自分だけではなく、相手と社会を想うことだ。相手にとって相手は自分だし、社会の中に自分はいる。助けるとは助けてもらうことでもある。不完全な我々は、不完全ながら助け合っているからこそ、今日も社会は回っている。
自分一人じゃない。それだけを忘れずに、できる範囲で、やればいい。
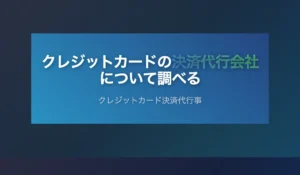
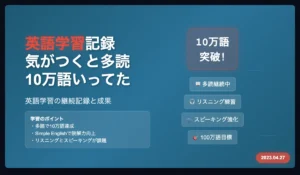
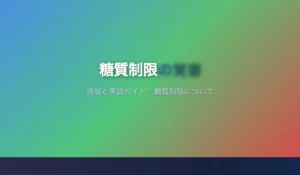

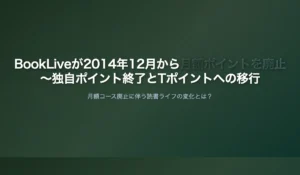
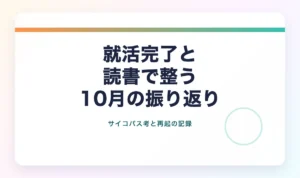

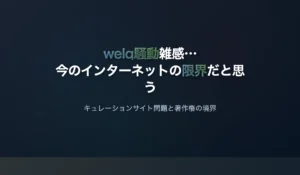
コメント