男女論は昔から語ると色々面倒臭い領域だったのだけれど、ただでさえ面倒臭かったテーマなのに、最近はさらにその面倒くささを加速度的に増しているようだ。
「女性らしく」「お嬢さま」はNG、指導内容に配慮 「彼氏」「彼女」は「パートナー」 LGBT女子中高アンケート - 産経ニュース
女子生徒だけの教育環境であっても、性の多様性を尊重する潮流を背景として、「女性らしさ」「お嬢さま」といったジェンダー(性差)を強調する表現が避けられる傾向が目立った。
一行で矛盾するコンテストでもしているのだろうか。女性らしさは性の多様性に含まれないらしい。
それにしても、性別を入学要件に取り入れている女子校で性差を強調するなとは、なんとも奇妙で自己否定的にも感じられるけれど、むしろこれぞまさに当世といったところかもしれない。矛盾を押しつけられた現場の教職員の労苦は想像するに余りある。しかしこの流れは教職員のみならず、対外的に人と話をする立場であれば否応なしに求められることでもある。世情のこの流れについて馬鹿馬鹿しいとは思うものの、その馬鹿馬鹿しいことで無駄にリスクを取りたくもないので、阿呆臭いと思いながらも表面的には従うことになるだろう。
このやっかいな事態に対する恐らくもっとも簡単かつ安易だが実用的な対策は、「男」「女」という単語を使わないことだろう。実際、僕は人と話をする時には親しい間柄を除いてなるべく使わないようにしている。さすがにトイレの案内の時には使わせてもらうが、しかしこれさえもそのうちに言えなくなるかもしれない今日この頃だ。
この施策は多様性の名の下に行われているはずだが、現実的に起きていることが「男」と「女」の消滅であるのは、実に皮肉である。いつもいつでも、本当のことは対外的な言葉ではなく、結果として起きている現実のほうだ。それは歴史の教科書を読み返すまでもなく、生きていれば誰しもが(多くの場合痛い目にあって)理解することでもある。
教職員の言葉から男と女をなくしても、現実の男と女が消えるわけではないし、なんなら依然として入学資格にもなっている。何も違わないのであれば同じように扱えるはずだが、そうしないのはそこに違いを認めているからに他ならない。いくらあるものをないように見せかけたところで、結局あるのだから、現実においては大きな歪みとなり、その解決は現場に丸投げされる。
性別にもとづく社会的な固定観念にとらわれず、個々人が自由に気兼ねなく生きられることは言うまでもなく重要なことだ。だが、いつの間にか作られているブラックリストの単語を使って糾弾されないかビクビクしながら生きることが自由な生き方なはずはなく、お題目がなんであれ、やっていることが力による抑圧であれば、そこに正当性を見出すことは難しい。
本音の議論が封じられたまま、着々と何かが進んでおり、しかもその真意が隠されているような気配があるために、当世のこの流れはとても不気味なのだが、そうは言っても個人にできることもなく、せいぜい違和感の表明くらいのものだ。それさえも実名では難しい世の中になった。この息苦しさはいつまで続くのだろうか。
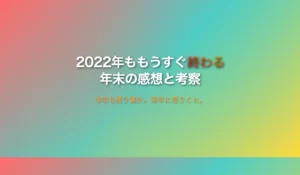


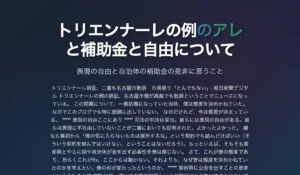

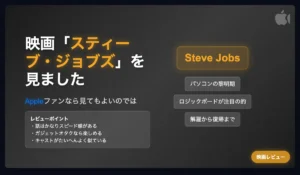
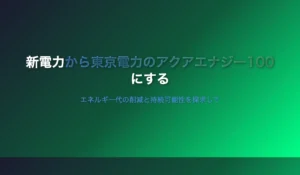

コメント