いつ頃からか、ナラティブという言葉をよく見るようになった。これの意味するところは明確に言うのは難しいのだけれど、自分の言葉で述べるなら、政治的価値観の反映された、特定の筋に沿った共感的で受け手の解釈・行動に影響を及ぼす枠組み、くらいだろうか。ITエンジニア用語で言うならば世界の見方のフレームワーク、といえばいいかもしれない。なんでもかんでも技術用語でたとえるのやめろ。まぁこのブログを見る人ならそちらのほうがわかりよい人も多かろう。
しかしITのフレームワークと異なり、政治的文脈において「ナラティブ」はあまり良いニュアンスを持っていない。具体的には、Qアノンなんかがそれにあたるとされる。陰謀論とかの説明で使われたりするわけだ。たとえばこんな風に使われる。
こうした観点で、「Qアノン」などの陰謀論も典型的なナラティブだ。「Qのクリアランスを持つ愛国者(Q Clearance Patriot)」を名乗るユーザ(通称:Q)は、説明や解説ではなく、問いかけや(一見意味不明な)単語の羅列を多く投稿した。こうした形式は、ユーザにとって、隠された陰謀の謎解きに参加する感覚を与え、Qアノン拡散の一因になったとされる。
ウクライナ戦争と「ナラティブ優勢」をめぐる戦い/川口貴久 - SYNODOS
この記事は批判的というよりは、客観的な目線で人々の動きを集合として捉えている、というほうが良いかもしれない。のだが、しかしやはり根底にはどこか「論理的ではないよね」という印象は受けるし、これはそうなんだろう。
ナラティブという言葉の使われ方から、僕は話者からこのようなニュアンスを受け取っている。
ぶっちゃけ彼らのこと全然理解できないんだけど、めちゃくちゃ影響でてるし、分析しないわけにはいかないし、かといって理解できない人たちの意味不明な行動、では何がなんだかわからないので頑張って解釈すると、なんかこう自分には意味不明だけど彼らには響く世界の見方があって、それにもとづいて彼らは動いている、これでどうよ。
というような感じ。
この解釈を見ればわかるように、僕はナラティブという言葉遣いそのものに対してやや批判的な見方をしている。
これは少し、悪意のある見方ではある。感情を抑制し、観察者としての立ち位置を徹底する時にもこういった言葉は出てくることはあるだろう。実際レポートなんか見るとそれに近いものが多い。上記の引用記事も、ナラティブの考え方をベースに特定の思想に寄らず両陣営に渡って相対化を試みている。
でも、僕はあまり使いたくない言葉だ。根本的な理解を放棄した理解のアプローチだと思う。理解しているようでしないというか、する意味もないというか。心情なんか理解できないから、事象として理解する、というアプローチだ。人間をダンゴムシかなんかだと思っているんだろうか。
そして実際、理解できない人たちのことは知覚的刺激に反応するダンゴムシの集団と置き換えたほうが、認知的負荷も心理的負荷も低くて済むだろう。あとはその知覚の源が何かについて考えればよいだけだ。人はなぜそうなるのか?という問いよりも、刺激物について考えたほうが楽だろう。ダンゴムシ迷路のごとく、刺激物を置いて自分が思うような方向に誘導できないものか?
もしかすると、実際それは効果的なのかもしれない。世界を浪花節で捉えるより建設的なのかもしれない。ただそうであったとしても、それならば、自分もそのダンゴムシ集団の中にいる一匹だと、その自覚はあるだろうか。ダンゴムシとしては、それだけ気になっている。
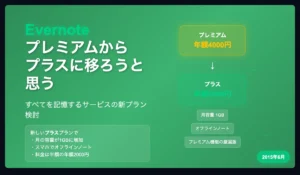
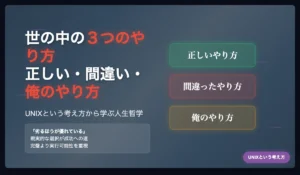

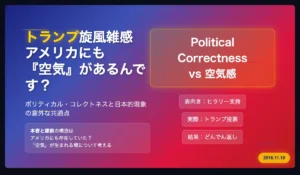


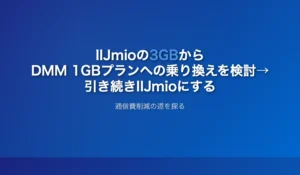
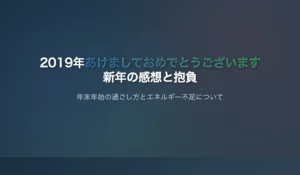
コメント