「それ、本人に言ったの?」
誰かの陰口を聞いたとき、こう問い返す人がいます。公正さを求める態度として、よく見かける言動です。しかし、これは本当にそうでしょうか。この言葉、発言する人の立場によっては、公正どころかむしろ不公正であることがあります。
勝率を高めることを目的にした見せかけのフェア
わかりやすい例を考えてみましょう。たとえば体が大きくて力の強い格闘家が、体が小さくて力の弱い虚弱体質の一般人に向かって、「正々堂々と戦え!」と言ったらどうでしょうか。正々堂々としているのは言葉だけで、実際には酷く不公正な態度だとわかります。
その裏には勝利への確信があります。絶対に勝てる条件を叩きつけるのは、合理的ではあっても公正ではなく、倫理的、道義的にはむしろ下衆ですらあります。
「悪口言うなら本人に言え」にも同じ構造があります。たとえば権力者や、またグループや組織において実質的に力を持つ者(学校で言えば人気者などもそうです)は議論において対等ではなく、彼らはまず強い立場にあることを自覚しなければなりません。強い立場の人間に面と向かって批判をするのは大きなリスクを伴う行為である一方、力の強い者にとっては有利な戦いです。
したがって、力の不均衡という現実の中で、強者のそれは勝率を高めるための行為であり、もしこれを自覚的にやっているのであれば、悪質な戦略的狡猾と言わざるを得ませんし、無自覚ならばただの傲慢です。いずれにせよ褒められた行為でないことだけは確かと言えましょう。
対等、あるいは弱者の言葉であれば?
しかし、それでは強者ではない者の言葉であれば良いのではないか、と考えられます。そして実際、それは恐らくYESです。
対等な立場の者が言う場合、それは「きちんと話そう」という意思の表れと言えます。批判者に対する反発心はあるかもしれませんが、それと同時にわかり合いたい、わかり合えるのではないか、という気持ちも受け取れます。
たとえば、職場で意見の食い違いがあった同僚同士が、一方の陰口を耳にしたもう一方に「それなら、直接言ってくれ」と伝える場面を想像してみてください。そこには、反発の感情と同時に「面と向かって話し合えば、何か解決の糸口があるかもしれない」という期待が込められています。
これは、第三者が対等なもの同士を引き合わせる仲介としても同じような効果があります。「君らはちゃんと話したほうがいいよ」という意味です。
そして弱者が言う場合、これは「せめて面と向かって言ってくれ」「目を合わせてくれ」という、もはや切実な訴え、願いとでも言うべきものです。
たとえば、学校で孤立している生徒が、自分の陰口を言っている同級生に向かって「言いたいことがあるなら、せめて面と向かって言ってよ」とつぶやく場面。そこには、自己防衛も、怒りも、哀しさも入り混じっています。それは、ただの倫理的主張ではなく、「人として尊重してほしい」という、切実な訴えにほかなりません。
こういったケースも現実にはあるため、「本人に言え」「正々堂々と戦え」という言葉自体に一定の倫理的、道義的な響きが伴ったのでないでしょうか。
強者が全体喚起として言った場合は?
考えられるケースとして、強者が言ったとしても、「本人」が強者自身ではないケースがあります。つまり、組織内におけるメンバ同士の態度について注意喚起として行った場合です。
これはやや微妙、実質的には恐らく不公正な結果になる、と思います。
たとえば、ある企業の上司が、職場内で起こっている陰口や不仲について「悪口は本人に言ってくれ」と言ったとします。このとき、上司自身が陰口の対象ではなく、部下同士の関係に対して注意喚起をしているという構図です。
一見、公平性を保とうとしているように聞こえるかもしれません。しかし、その職場において発言力の強い部下と弱い部下がいたとしたらどうでしょうか。上司のこの発言は、実際には「弱い立場の者が強い者を批判する自由」を封じる方向に作用し、強者に有利な秩序を温存する結果になる可能性があります。
しかも、その「本人に言え」という言葉が、職場における非公式な監視の空気を強め、結果として誰も何も言えなくなるということもありえます。つまり、形式的には中立的でフェアに見えても、実質的には一方に有利に働く構図が生まれるのです。
もしも、全員が形式的にも実質的にも対等であれば、これは論理的には「フェアであれ」という意味になるかもしれません。しかし現実的に、そんなことはありえるのでしょうか。そしてもし本当に全員が対等な立場である場合、果たしてわざわざこんなことを言わねばならないような状況になるものでしょうか。つまり、たいていの場合は、組織内の弱者の口を一方的に噤ませるだけではないかと思われます。
「誰が」と「何を」を考える
誰が言うかより何が言うかが大事、とはよく言ったもので(特にネット黎明期の匿名掲示板世代には馴染みのある考えたではないでしょうか)、実際中身を見るべき時は確かに存在します。特に事実の指摘や科学的な考察、論理的な言説については、肩書きではなく言葉の中身を見るべきです。
一方で言葉の真意、意図といったものは、その人の立場抜きに語ることはできません。
そして「誰が」と「何を」は常に両面あります。ただし、どちらがどれだけ重要かは、中身によります。両方見るべきときもあれば、片方はさして重要でない時もあります。
今回の記事でいえば、私は「悪口は本人に言えとは一見公正を求めているようだが、その人の立場によっては傲慢・狡猾でありえる」といっているわけですが、これは前提に基づく論理の展開であって、私が誰であろうと変わりはありません。しかし「私がこの記事を公開した意図」は、私の立場抜きに合理的な推察をすることは難しい(一般論としてならば推察できるでしょうが)。ただし、今回のような記事で意図を勘ぐる意味は誰にもありませんから、それが問題にならないというだけです。
一方で、「悪口は本人に言え」「正々堂々と戦え」といったような倫理的要求は、中身よりもむしろ意図を重視すべきです。したがって、その人の立場、そして言われている自分の立場、さらに自分たちを取り巻く社会的環境についてまず考える必要があります。
それは誰にとっての正しさか
最後にやや抽象的な話になりましたが、要するに、「誰にとっての正しさか」を考える視点こそが、本当の公正を見抜くために必要だということです。表面的な正しさに隠れた力関係を見抜くこと。それは、誰かを正す前に、まず自分自身が公正であるかを問い直すことでもあるのです。
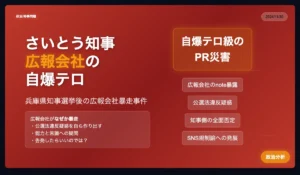
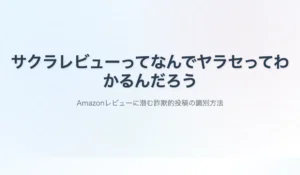
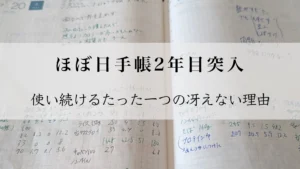
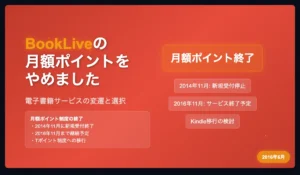

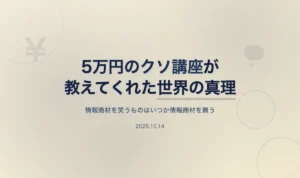
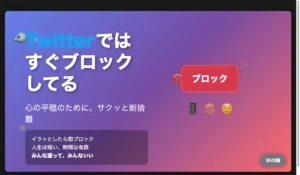

コメント