「これがベストプラクティスです」と言われるようになったのはいつ頃からなのだろう。僕が業界に入ったときにはもう使われていたが、金科玉条のように掲げられるような印象まであるのは割とここ最近のようにも思う。
誰が「ベスト」だと決めるのか?
考えてみると、ベストプラクティスとはけったいな言葉だ。俺が俺のベストを決める分にはそいつの勝手だが、それを他人に従わせる圧力のようになると、話が変わる。いったい誰がどんな権利で「ベスト」を決めるんだろう?そして何故みんなそれを「ベスト」だと認めるのだろう?
しかし実際、他ならぬAWSに「DynamoDBは少ないテーブルを保つのがベストプラクティスです」と言われれば、それは頷くしかない。実際そのほうが良いし、そのように仕様自体が設計されている。仕様の策定者にそう言われれば、やはりそう考えるのが妥当であろう。なので、仕様の変更と共にベストプラクティスは変化する。実際、DynamoDBはかつて1つのテーブルが最良とドキュメントに書かれていたものだ。当時はテーブル間のアクセスに制約があった。
他にもデファクトスタンダードからくるものも、ベストプラクティスと言われることがある。PEP 8自体はスタイルガイドに過ぎないし、PEP 8にもこれがベストプラクティスとは書かれていないが、PEP 8に従うのがベストプラクティス、みたいな言い方はある。
いずれにせよ、ベストプラクティスの成立条件としていえそうなことは、権威があり、その根拠も十分であるので、納得する人たちが多数いる、ということだ。
誰がAIのベストを決めるのか?
さてここで、AIについて考えたい。いったい、AIプログラミングのベストプラクティスはあるんだろうか。このようにAIを使うのがベストプラクティスです、というのは、少なくとも今はなさそうだが、今後生まれる可能性はあるんだろうか。
これは多分、非常に難しい。っていうか存在しえないと思う。理由は簡単で、誰もAIの挙動の原理を説明できないから。
誰もAIのことがわからないので、AIのベストを決める能力があると見られる根拠がない。よって、誰もベストを決められる権威を持ち得ない。
これが人間のベストプラクティスです
同じようなものとして、人間という存在がある。当たり前だが、人間関係にベストプラクティスは存在しない。「友達作りのベストプラクティス」なんて記事はジョークにしかならないし、「女を落とすベストプラクティス」は三流雑誌確定演出。その代わりにあるのは、「つらい時に考えるべき10のこと」だったり「7つの習慣」だったりする。
7つの習慣が役に立つかどうかは別として、少なくとも影響を受けた人は多いだろう。しかし「この7つの習慣が人間のベストプラクティスです」と言う人はちょっと見たことがないし、いたら恐らく読んでいない。
これは誰も人間の本当のところなんてわからないからだ。まぁ「俺は人間のことがわかる」と言っているやつはたくさんいるかもしれないが、実際にそうだと大勢に認められたられた人はいない。
よって、人間関係のベストプラクティスは誰にも決められない。決めてもそれを認められない。
AIと人間は同じではないが、その振る舞いの原理が本当のところわからない、という点では共通である。したがって、誰もベストを決める権威になれない、という点も共通と考えられる。
プラクティスはある
以上より、AIにベストプラクティスは存在しないだろう。少なくともAIの原理を完全に説明できる存在が認められるまでは。これは認められることが大事なのであって、実際にそれができるかは必ずしも必要条件ではないため、可能性としては「ベストプラクティスということになっているもの」は生まれうる。まぁそれはけっこうディストピア感あるのだが。
まぁいずれにせよ、一つ言えることは、当代を生きる僕らはAIのベストプラクティスを待っているのは無駄、ということではなかろうか。つまり、ベストプラクティス以前の状態に立ち返る必要がある。
たとえば、最近僕が読んでいるのはカーニハンのプログラミング作法だが、この原題はTHE PRACITCE OF PROGRAMMINGである。
ベストプラクティス以前にも、プラクティスはあった。カーニハンはベストプラクティスを示さないが、プラクティスは示した。そしてこの本は1999年の本だが、今もためになる。2015年のベストプラクティスとされたもののほとんどが2025年現在読まれないと思うが、25年前に示されたベストではないプラクティスが、今なお使えるというのは、なんだか示唆的だ。(なお読んでいるといったが身についているかは別である🥺)
これは人間の話も同様で、7つの習慣はベストプラクティスではないかもしれないが、プラクティスではあるかもしれない。カーネギーの本も人間関係のベストプラクティスではなかろうが、プラクティスではあるかもしれない。プラクティスはいつでもどこでも適用できるわけではないが、時代を超える普遍性がある。
このように考えると、ベストプラクティスがない、というのはなんだか心細いように思えるのだけれど、しかし実はあるべき姿に立ち返っているのではないか、とも思える。
とどのつまり、圧倒的な権威が素晴らしい方法を提示してくれることを期待するのではなく、今一度、一人一人が、自分でプラクティスを探し、他人のプラクティスを学び、自分なりの作法を築き上げていくという、よくよく考えてみると既にやってきたことについて、改めて自覚する段階にきているのではないか。
なのでまぁ、僕なりに考えたことやったことは記録していきたいし、皆にも記録してほしいなぁと思う。


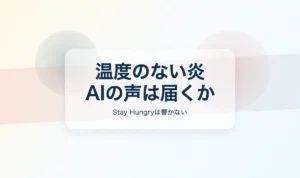
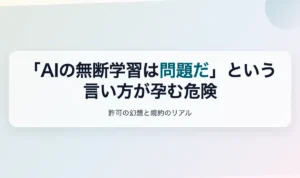


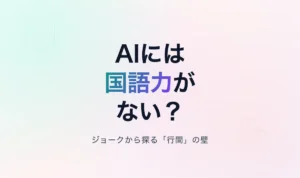
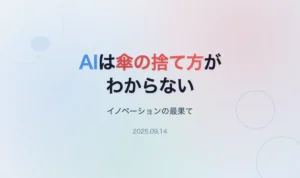

コメント