TLで「自由ソフトウェア」なるものが流れてきた。
「『自由ソフトウェア』の開発にDiscordを使わないで」という主張 - GIGAZINE
自由ソフトウェア?と思ったけれど、つまりフリーソフトウェアだね。いつの間にか日本語の訳語として自由ソフトウェアという使われ方がされるようになっていたのだねぇ。
これは確かにそのほうが良いかもしれない。というのも、日本では既にフリーソフトウェアとは「何故かわからんが無料で配布されているソフト」くらいの認識になっており、その精神はまず理解されていない。実際既にOSSにもそういうニュアンスが込められることがある。このへんは非技術領域で技術を使いたがる人と話した時に顕著だと思う。
しかし考えてみると、そういう僕も自由ソフトウェアの精神みたいなものは、あまり考えずにここまできてしまったなぁと思う。だってなかなかそれじゃ食べていけないからね。みんな苦労している。
関連して、GIGAZINEには2年前のRed Hatがソースコードの一般公開をやめた時の記事を貼っていて、つい読んでしまった(GIGAZINEのこの回遊させる記事チョイスは見習う必要がある!)
- Red HatがRHELソースコードの一般公開をやめて顧客限定に、自由ソフトウェアの原則を軸にしてきたLinux関係者たちから猛批判を受ける - GIGAZINE
- 「下流プロジェクトは無価値」とソースコードの一般公開を取りやめたRed Hatに対してAlmaLinuxの開発チームがこれまでの貢献を力説 - GIGAZINE
RHELはLinux関係なんだからGPLなんでは?と思ったけれど、GPLというのは利用者に公開する義務はあるけれど、必ずしも一般公開する義務はないのだってね。で、RHELはその規約で、利用者にはソースコードの配布もする……が……再配布とか舐めたことしたらもう世話してやんねぇ、というストロングスタイルによって、実質的な制約を設けた、ということらしい。
しかしこれでは、条項は遵守しているかもしれないが、GPLの精神を踏みにじっているんじゃないのか、と思うし、実際そうだから批判を受けるのだろう。ただRH側も自己正当化のためか知らないが、下流プロジェクトは無価値、貢献していない、本当のOSSにとっての脅威とまで言ってめっちゃ喧嘩売るのは、アングロサクソンの血が為せる業なんだろうか。どっかの政治家が、自分に反するのは真の支持者じゃないとか言ってたけど、こういうときに「真の」「本当の」がつくのって自己防衛的な深層心理なんかね。
Red HatからすればOSの基盤を作ってきたと言いたいところなのかもしれないが、これは恐らく因果が逆転しているところがある。Red Hatがいたから、Red Hatクローンを作らざるを得なかった、というのが下流プロジェクト側の本音でもあるんじゃなかろうか。アメリカに締め出された中国が、AndroidベースでモバイルOSを作るのは、技術力の問題というよりはエコシステムの問題だと思うが、本質的にそれと同根であろう。
今のWindowsやMSオフィスにしてもそうだが、誰も機能を真似できないのでは無くて、プロプライエタリな秘匿されたフォーマットが業界標準になっているために、誰も太刀打ちできない、という状態だ。実際オフィスソフトなんかは、機能的には色々なメーカーが出しているのだが、もっとも求められているのは結局のところMSオフィス互換であること、なのが実情だしね。
これは互換性、標準化の戦争というべきもので、ここにあるのはもはや技術力より政治力である。これは、どちらかといえば地位に近い。エンジニアというよりは貴族である。最近のGoogle(YouTube)やMSやXの振る舞いは目に余ると思う人はけっこういるのではないかと思うのだけれど、その力の源泉は、決して圧倒的な技術力ではなく、築かれた地位、なんだな。RHも是非ともその一員になりたい、ということであろう。
どういうわけか、人間の社会の中ではそういう貴族が生まれ、貴族が増長して庶民を舐めくさりきって、我慢ならない庶民が貴族野郎どもを血でわからせる、というのが歴史のサイクルになっている。今もそのサイクルからは抜け出せていないように思うが、今どのへんにいるんだろうねぇ。
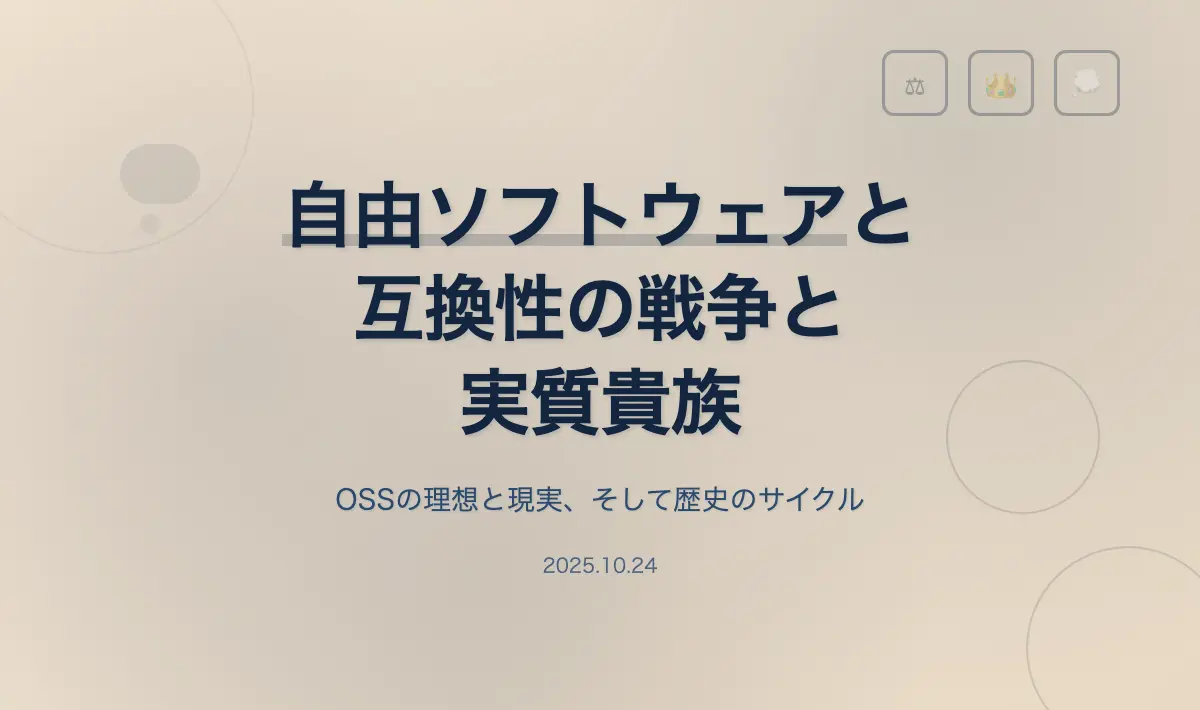

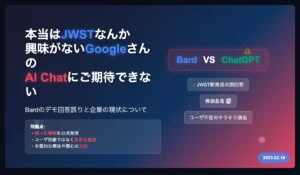
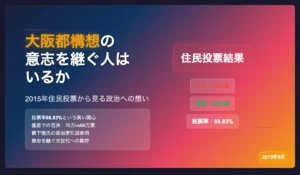
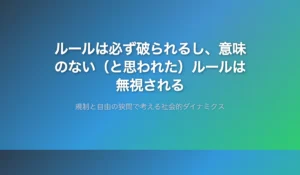


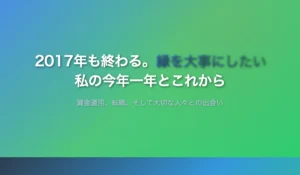
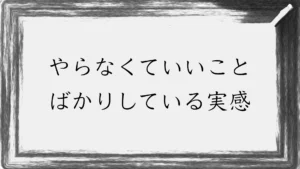
コメント