最近、AIが「無断で学習している」と批判されることが増えている。しかし、ここで無断という言葉を用いることは、当人の意図に反した結果をもたらす危険があるかもしれない。
無断学習がいけない、と言ってしまうと、「無断でなければ良いのか」つまり「許可を取れば良いのか」という話になる。これは肯定せざるを得ない。あるいは「取れるものなら取ってみろ」と思うかもしれない。
しかし、これは世の中を少し甘く見ていると思う。許可を取ればいいと言われれば、彼らは許可を取る。たとえば、noteはGoogleとの提携後、AI学習への同意をデフォルト設定にした。Xも同様だ。
我々の多くはXの規約に同意している。Facebookの規約に同意している。Googleの規約に同意している。自分はしていないという人もいるかもしれない。だがそれが少数派であることは認めるだろう。
多くの人は、規約を理解し納得しているわけではない。ただ必要のために同意の体裁を取っている。数千万円のマイホームの購入であれば、契約書の隅々まで熟読するだろう。しかし、Webサービスのアカウント一つ取るためにそれをする人は多くない。
もっといえば、サービス側も本気で読まれると思っていない。そもそもサービスの中の人たちだって、プライベートでは碌に読んでいないのだ。その感覚を彼らもわかっている。読まれない規約は、企業の法的リスクを目的としており、ユーザの同意を本気で求めているわけではない。我々はそれを知っている。
無断学習はいけないという理屈の先は、結局、規約の中に許可を埋め込まれるだけだ。そして我々はその規約に、実際的には抗えない。
確かに、AIの学習には多くの問題があると思う。しかし、それは止めようとして止められるものではない。学習は、技術的にも構造的にも、すでに世界のあらゆるところで進行している。それを「無断」という倫理の枠で捉えようとしても、最終的には資本を持つ側が“正しい許可”を盾にして支配を強めるだけだ。
本当に問うべきは、「学習」が無断かどうかではなく「学んだ結果をどう使うか」ではないか。
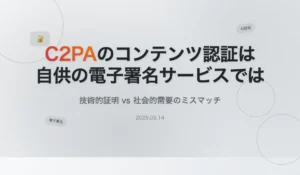
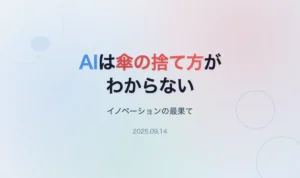
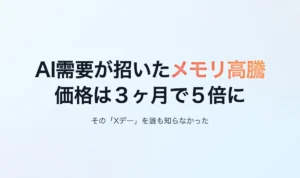


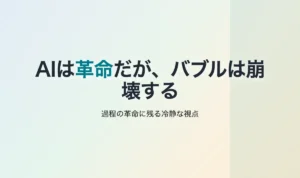

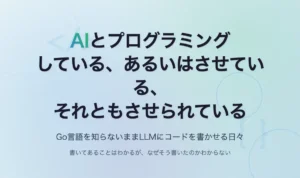
コメント